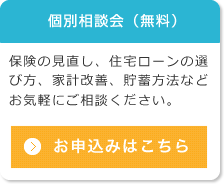遺言書と家庭裁判所の関係
遺言書は、財産の分配や相続に関する故人の意思を明確に示す重要な書類ですが、場合によっては家庭裁判所が関与することがあります。本記事では、家庭裁判所が関与するケースやその役割について解説します。
1. 遺言書の検認と家庭裁判所
遺言書の種類の中でも、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は、家庭裁判所での「検認」という手続きを経る必要があります。
(1)検認とは?
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在や内容を確認し、その「形式」が適正かどうかを調査する手続きです。検認を受けないと、遺言書を相続手続きに使用することができません。
ここでのポイントはあくまでも「形式」が適正かどうかを調査するという点であり、重要な「中身」の記載内容が法的に有効かどうかの調査をするものではないという点にあります。
(2)検認が必要な遺言書
- 自筆証書遺言:遺言者が自筆で作成し、署名・押印した遺言書
- 秘密証書遺言:遺言者が作成し、公証人と証人が関与して封印された遺言書
一方、公正証書遺言は、公証人が作成しているため、検認の必要はありません。
(3)検認の手続き
遺言書が発見された場合、遺言を執行する前に、相続人や利害関係者が家庭裁判所に対して検認の申立てを行います。手続きの流れは以下の通りです。
- 申立て:遺言書を発見した相続人または受遺者が家庭裁判所に検認を申し立てる。
- 裁判所での開封:遺言書が封印されている場合、裁判所で開封し、内容を確認。
- 検認証明書の発行:検認手続きが完了すると、遺言書が法的に有効であることが証明される。
この手続きを経ることで、遺言書の改ざんや偽造を防ぐことができます。
2. 遺言執行者の選任と家庭裁判所
遺言の内容を実際に執行するためには、遺言執行者(遺言の内容に従い実務的に手続きなどをする人)が必要となる場合があります。遺言執行者が指定されていない場合や、指定された執行者が辞退した場合は、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。
(1)遺言執行者の役割
- 相続財産の管理
- 債務の弁済
- 相続人間の調整 など
家庭裁判所が選任することで、遺言の内容が適切に実行されるようになります。
3. 遺言無効確認訴訟と家庭裁判所
相続人の中には、遺言の内容や作成過程に疑問を持つ人がいることがあります。その場合、「遺言無効確認訴訟」を提起することができます。
(1)遺言が無効となる可能性のあるケース
- 遺言者が認知症などで意思能力がなかった
- 遺言が詐欺や強迫によって作成された
- 法的要件を満たしていない(例えば、自筆証書遺言で日付の記載がない など)
遺言無効確認訴訟は家庭裁判所ではなく地方裁判所で争われますが、相続の調停や遺産分割協議の中で家庭裁判所が関与することもあります。
まとめ
遺言書と家庭裁判所は、検認、遺言執行者の選任、遺言無効確認など、さまざまな場面で関わります。特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合は、検認という別の手続きの必要性を理解しておく必要があります。
一般的に、これらの点や記載内容が法的に無効にならないようにするためにも、公正証書遺言という選択肢は非常に有効であると考えられています。
そして、相続人同士のトラブルを避けるためにも、信頼できる遺言執行者を指定したり、事前に専門家へ相談することが推奨されます。家庭裁判所の役割を理解し、適切な相続対策を講じることで、円滑な相続を実現しましょう。
遺言のお悩みについては、専門家の無料相談を利用
羊商有限会社では地域の方々の遺言書作成について情報提供および無料の相談を実施しております。
ご希望の方は、ぜひ以下のリンクをご活用ください。

- Posted on 3月 8, 2025 at 2:41 PM
- Written by プロフィナンシャルサービス_ブログ
- Categories: 相続支援